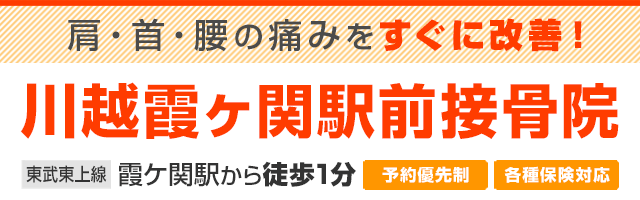眼精疲労

こんなお悩みはありませんか?

ドライアイ
→眼球の表面が乾燥する病気です。目を酷使する人やコンタクトレンズを使っている人がなりやすく、しばしば眼精疲労を伴います。
緑内障
→網膜の視神経が障害されて視野が狭くなる病気です。しっかり施術せずにいると、失明することもあります。緑内障の患者さんは眼圧が高い人が多く、眼圧が高いときには頭痛が起きやすくなります。
白内障
→白内障は水晶体が濁る病気です。そのために視力が低下したり、まぶしさを感じたりして、眼精疲労の原因となります。白内障は手術で治せますが、手術後に少し見え方が変わるので、それが眼精疲労を起こすこともあります。
斜視(しゃし)
→物を見るときには両眼が連動して動き、わずかに寄り目になって視線を一点に合わせます。両目の視線が一致せずに左右別々の方角を向いてしまうことを斜視といい、眼精疲労の原因になります。
斜位(しゃい)
→物を見るときには視線が一致するものの、視線を合わす対象がない場合に、左右の眼が別々の方角を向いていることです。物を見る際に、左右の視線を合わせる努力を強いられることになり、眼精疲労が起きます。
眼瞼下垂
まぶたが垂れ下がってくる病気です。視野の上のほうが見えなくなるので、物を見るときに頭を後ろへ反らすなどしなければならず、眼精疲労の原因になります。
眼精疲労についてで知っておくべきこと

「目の疲れ」と「眼精疲労」の違いは、休息や睡眠をとった後に回復するかどうかにあります。目に不快感があり、睡眠をとるなどして目を休ませても症状が軽減されない場合は、眼精疲労の可能性があります。
また、度数が合っていないメガネやコンタクトレンズを使い続けていて、気づかぬうちに目に負担をかけていることもあります。
目の痛みやかすみ、ぼやけといった違和感・不快感だけでなく、全身症状が現れるのも眼精疲労の特徴です。首や肩のこりや痛み、頭痛のほか、疲労感やイライラ、吐き気といった症状が現れる場合もあります。
症状の現れ方は?

眼精疲労は「目が疲れる、ぼやける」「目が痛い、充血する」「目が重い、しょぼしょぼする」「眩しい」「涙が出る」といった様々な症状を呈し、肩こりや疲労感、頭痛、めまい、吐き気などの体の症状を訴えることもあります。
全身の健康に問題があると、目にかかる負荷に耐える力が足りなくなってしまいます。また、疲れやすい体質や、夜勤や海外出張などによる生体リズムの変調、またストレスによって自律神経に影響があると、まばたきや涙の量が減り、目の疲労が進むことがあります。
緑内障や白内障の他、脳神経疾患、高血圧、低血圧、糖尿病、自律神経失調症、月経異常など目以外の病気に伴って眼精疲労の症状が現れることもあります。
その他の原因は?

近年、パソコンやスマートフォンなど、目を介したコミュニケーション手段が多用されるようになり、視覚の重要性がますます高まっています。しかし、それと同時に目への負担が増し、目の疲れや乾きといった不快症状に悩まされる方が増えているのが現状です。
また、目の不調や病気は加齢によって現れることが多く、50歳以上の方のほとんどが何らかの目のトラブルを抱えているという報告もあります。
目はデリケートで不調が起こりやすい器官であり、少しでもトラブルがあれば生活の質に大きく影響します。さらに、目の健康は全身の健康や心の健康にも密接に関わっているため、日頃から目の健康を気遣うことは、心身の健康を保つための重要なポイントのひとつともいえます。
眼精疲労を放置するとどうなる?

眼精疲労の原因としては、長時間同じものを見続けること、パソコンやスマートフォンのブルーライト、ドライアイ、度数が合っていないメガネやコンタクトの使用などが挙げられます。
眼精疲労を放置してしまうと、眼疾患の発症リスクが高まるほか、精神的なストレスが増す、頭痛や肩こり、吐き気といった体の不調が現れることがあります。
他にも、睡眠の質が低下するなどの症状が現れることがあり、個人差はありますが、日々の生活に支障をきたす可能性もあります。
このような事態を避けるためにも、適度に目を休めたり、目を温めるなどの予防が大切です。また、パソコンやスマートフォンを使用する際には、ブルーライトカット眼鏡を利用したり、寝る直前までスマートフォンを使用しないなどの工夫をし、目を守ることが重要です。
当院の施術方法について

眼精疲労を軽減するために当院では「極上ドライヘッド」という施術方法をおススメしております。
極上ドライヘッドの効果としては、自律神経の調整が挙げられます。副交感神経を優位にし、サーカディアンリズムを整えることが期待できます。視力のピントを合わせやすくなり、視野が広がる効果もあります。また、脳疲労やVDT症候群から来るストレス、不定愁訴など現代病の軽減が期待できます。
さらに、筋膜を刺激することで頭部の血行が良くなり、疲労の元となる乳酸や老廃物が流れやすくなります。脳脊髄液の巡りもスムーズになることが期待できます。
脳疲労については、大脳新皮質、大脳辺縁系、間脳がストレスによって影響を受け、自律神経系にまで影響が及ぶことが示唆されています。
施術の頻度については、一般的に1日3回の筋膜リリースを2週間続けることで身体に変化や効果が現れることがあります。現実的にその回数を施術することは難しいですが、3ヶ月継続することで効果が表れる方が多いです。
継続が重要です。最低でも週3回の施術をお勧めします。継続が難しい場合は、期間で調整を行いながら進めていきましょう。
改善していく上でのポイント

まばたきを意識し、休憩をとることが重要です。目を休めることが一番です。まばたきをすると、目の周りの筋肉がストレッチされるため、ドライアイ予防にもつながります。意識的にまばたきをしましょう。仕事で長時間パソコン作業など、集中して文字や画像を追う作業が続く場合は、1時間に10分程度の休憩をとり、目を休めるとよいでしょう。
目の疲れには「後頭部」をもみほぐすとよいです。それと合わせて行いたいのが「後頭部」のマッサージです。首と頭の境目の深層には「後頭下筋群」という小さな筋肉が集まっています。この後頭下筋群は、首や頭が目の動きと連動して動くのを制御する働きがあります。目を使い過ぎると、後頭下筋群も働きすぎて硬くなってしまうことがあります。
監修

川越霞ヶ関駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:千葉県松戸市
趣味・特技:車中泊旅行、野球